「脱サラして起業したい!」と思う方は多いと思います。
ただ、それ以上に不安やリスクも多く、なかなか一歩踏み出せない人も多いでしょう。
前回までは、私の経験を元にやっておいて良かった事ややっておけば良かったと思った事などを紹介しました。
この記事では、実際に私がリアルに経験した脱サラ~独立・起業に至るまでの体験をもとに、実際に私が経験したリアルな道のりを紹介しながら、同じ道を目指す方の背中を後押しできるようになればいいなと思います。
起業までの道のり【脱サラ編】
なぜ脱サラを決意したのか?
私は高校卒業後に調理師の専門学校に進学しました。
なぜ調理の道に進んだのかというと、高校時代はサッカー部に所属していて、ずっとサッカーに明け暮れていたこともあって進路のことを何も考えていませんでした。
その時に母が私に
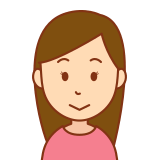
料理人になって
自分のお店を持ってくれたら嬉しいかな。
それが私の夢かな。
ただ、当時は料理に対して楽しむ事ができず、卒業後は全く別の道へ進む選択をしました。
工場勤務・製造業という仕事をして、最初の頃は加工業が楽しくなり仕事に没頭していたのですが、ずっと続けていくうちに25歳くらいの時に

このままでいいのかな?
自分で何か起業して、がむしゃらにやってみたい‼
という気持ちに変化していきました。
キッカケは、周りの影響です。
私の周りは起業家が多く、日々奮闘している姿を見ているうちに刺激を受け
スキルアップの転職ではなく、人生のスキルアップの為の【起業する】という選択肢を意識するようになりました!
そこからどのジャンルで勝負しようか考えた時に、母が夢だと言った”あの言葉”を思い出しました。
せっかく高いお金を払って料理の道へ進ませてくれたのに、大した努力もしないまま諦めてしまった過去。
もう一度、母への恩返しのつもりで再度料理の世界でチャレンジしてみようと思いました。
こうして、私の起業家への道が始まりました!
私が実際にした覚悟の決め方
起業家を目指すことを決めたはいいものの...
会社員時代の収入や福利厚生などの安定がなくなるわけですから、最初の頃は自分の中で

本当に脱サラしていいのか?
安定を捨ててまでやる覚悟はあるのか?
起業するためには、勤めている会社を辞めなければならないのですが、やはり脱サラする勇気なんてなかなかありませんよね^_^;
そこで自分が起業するための覚悟として目標を作ろうと思いました。
そこで決めたのが
調理師免許の取得です‼
30歳までに調理師免許を取得できたら、会社を辞めて起業しよう。
もし取得できなかったら、このまま会社員でいようと決意しました。
そこから毎日、猛勉強して
29歳の時に調理師免許を取得することができました。
そして30歳の時に、とうとう会社を辞めて修行先を探すことになるのですが。
この時は、色々なジャンルの料理を経験して1番楽しかった料理をやろうと決めていました。
そして
最初に飛び込んだのが
焼き鳥屋でした!
起業までの道のり【修業時代編】
修業時代の始まり
今、記述したように色々なジャンルを経験しよう思ったのですが、この最初に飛び込んだ焼き鳥屋が、自分の中で凄くハマりました。
串打ちや焼きの難しさだったり、営業時のお客様との距離感だったり。
全部が自分にとって、上手くは説明できませんがしっくりハマった感じがしました。

素直に極めたいなと思いました!
ただ極めるなんて簡単なことではないし、一生無理な事だと思うけど、初めてその無理な事に挑みたいと・・・
一生を費やしたいと。
こんな風に思ったのは、初めてかもしれないですね。
雑学の勉強をしだしたのも、ちょうどこの時期くらいだったと思います。
勉強すればするほど、知らないことを知れば知るほど、とにかくのめり込んでいました。
そもそも雑学を勉強したのも、営業中はただ焼き鳥を焼くだけでなく余裕がある時はお客様との会話も楽しむ時間でもあります。
普通の世間話やお客様の仕事の話をする中で
焼き鳥についての質問された時に答えられなかった時がありました。
焼き鳥屋なのにわからないってダメだなと思ったのがキッカケです。
修業時代に学んだこと
当時は技術面の勉強も同時にしていたので、結構大変でした。
今だから言いますけど(笑)
でも、いつかは覚えなければいけないこと。
とにかく多くの大変な思いや経験をして、独立するまでに頭と体に技術、知識をとにかく叩き込む。
それが【修行時代】です!
この修業時代は、「経営のリアル・ノウハウを」を知るための貴重な時間です。
自分が思う理想と現実のギャップを感じる事や、必ずどのお店にも地道な努力と積み重ねが重要な土台であるということを知る事です。
私が実際に修業して学んだことは
- 小さなことを毎日繰り返し積み上げる習慣
- 他責ではなく自責で見る視点や観察力
- 仲間やお客様との信頼関係の大切さ
こうして少しづつ独立へ向けて、歩みを進めていき・・・
そして、次に決めたのが【修業期間】です。
修行期間の設定
焼き鳥屋で修業するにあたり
まず設定したのが修業期間!

自分の中で勢いとかモチベーションの事や年齢的な事を色々と考えて、あまり長すぎてもダラダラしそうだし、短すぎても知識や技術面の習得に不安があったので...
そこで決めた修業期間が【2年】です!
この【2年】という期間は、長そうで短いというのは自分でもよくわかっていたので
2年と決めたからには
とにかく時間を無駄にしないように日々励もうと決意しました!
自分の性格は自分がよくわかっているので、この修業期間中は友人との誘いも断ったりする事もしばしば...
とは言えども、息抜きも必要なので、たまには遊んだりもしました。
修業時代の苦労と姿勢
とにかく毎日が苦労の連続でした。
毎日の仕込み、串打ちの大変さ。

最初の頃は当たり前の事だけど、スピードも遅いし見た目もキレイに串打ち出来ずで、悔しい毎日でした。
ただ、僕はずっとサッカーをやっていたこともあってか、とにかく根性だけはあったので

毎日へこたれずに出来るようになるまで何回も挑戦しました!
そして同時に焼きの習得や技術向上の他にも、接客・経営の知識など覚えることがたくさん!
ほんとに遊んでる暇なんてありません。
1分1秒大切に過ごさなければと思っていました。
当時、修業先の社長は口数が少ない方で、こちらから聞かない限りは何も言わない、教えないタイプでした。
僕自身も何でもすぐ聞くのは自分の為にならないと思っていたので
まずは自分で考えて、それでもわからなかった時に質問するようにしていました。
これから先、自分でやるようになったら聞ける人も教えてくれる人も助けてくれる人もいません。
だから
自分で乗り越える力
判断力を
身につけなければなりません‼
修業というのは知識や技術だけを学期間ではありません。
判断力や対応力
適応力も同時に身につけるのも
修業の1つでもあります!
技術や知識は、勉強・練習すれば、個人差はあるけれど徐々に身についてきます。
しかし、判断力や対応力は勉強や練習だけじゃなく日々の経験の応用・積み重ねになります。

これは今後自分で企業を考えている方は必要な事なので、参考にしていただければと思います。
独立の決断と準備
私の場合は、自分で設定した修業期間は2年。あっという間に【2年】という月日が経ち、ついに独立の時がきました‼
修行期間や独立のタイミングは自分で決めるもの。
自分の力でやっていけると手応えを感じたのであれば、その勢いのまま前に歩みを止めないことが重要です!
その独立前には、下記の準備をするとスムーズに進みます。
- 保険所への連絡
- 開業届の提出・青色申告の準備
- 会計士へ依頼するのか、しないのか
- メニュー表の作成(自主作成or依頼)
- ホームページまたはSNSの作成(新規顧客へのアプローチ)
独立後の現実から見る修業で得る経験の大切さ
どんなに修業しても準備をしても、独立後は全く別物でトラブルは付きもの。
でも、そんな時に真剣に修業時代を取組んだり経験があったおかげで、冷静に対処できたり少しずつ信頼を積み上げていくことができます。
今振り返り思うことは
脱サラ~修業~独立というプロセスは、時間がかかろうとも全てが必要な経験・ステップであったなと思います。
特に修業時代での経験は、独立後の経営において今でも基礎となっています!
まとめ:最後にこれから起業を目指す人へ
私は30歳の時に脱サラして2年間の修業を経て独立し、10年以上続けてこれました。
しかし、商売は苦労の方が多いです。でも、会社員の時よりも比べ物にならないくらい楽しいです‼
脱サラや起業することは勇気のいる決断だと思います。
しかし、しっかり準備し修業時代にたくさん苦労し、学び、経験を積みながらステップを踏めば必ず乗り越えられます!
焦らず、着実に進むことがとても大切です。
これからの時代は、いかに自分が自分らしくいるか。
昔に比べれば選択肢は多いと思いますので、何かに迷っている人は可能性は誰にでもたくさんあると思うので、一歩を踏み出してみて下さい!
遠回りがいちばんの近道。
最後まで読んでいただき誠にありがとうございました!






コメント